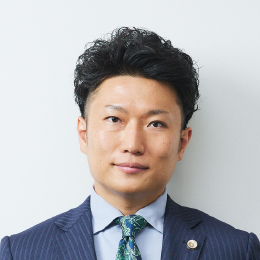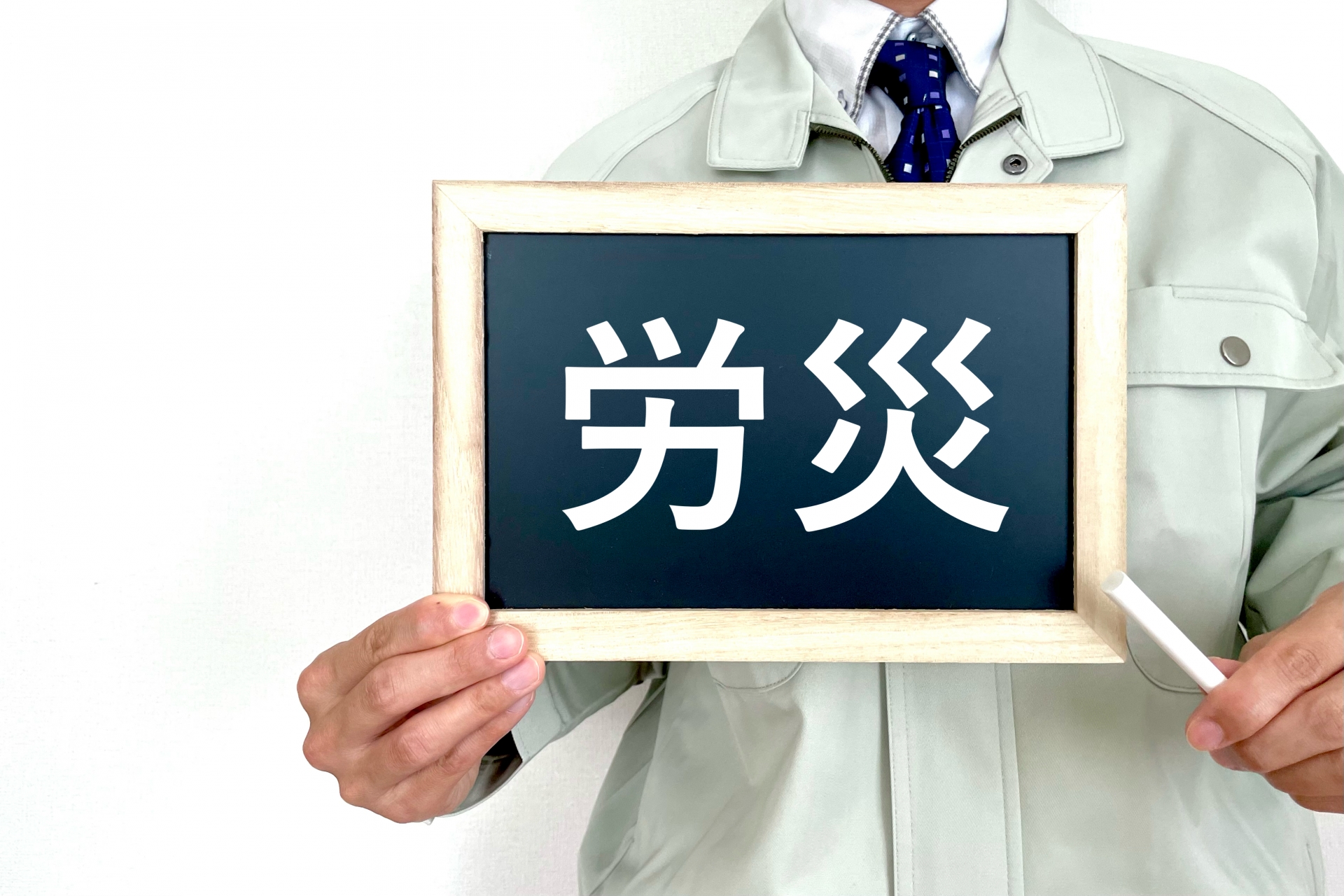
労災事故は、労働者がいる限り、発生する可能性があります。
労災事故を予防するため、日頃からいかに対策するかが重要ではありますが、ここでは労災事故が発生してしまった場合に、どうして労災隠しをしてはいけないのかについて、会社側の視点で様々なデメリット解説して参ります。
労災隠しをすることのデメリットとは?
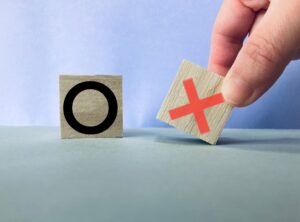
弁護士の視点から、使用者(会社側)が労災隠しを行うことのデメリットを解説します。
労災隠しは、短期的なコスト回避を狙って行われることがありますが、発覚した場合のリスクは非常に大きく、長期的に見れば企業の存続に関わる深刻なダメージにつながりかねません。
主なデメリットは、以下のとおりです。
① 刑事罰のリスク(労働安全衛生法違反)
労働安全衛生法第100条は、労働者死傷病報告の提出を義務付けています。
労災隠しはこの報告義務に違反する行為であり、同法第120条に基づき50万円以下の罰金という刑事罰の対象となります。
これは単なる行政指導ではなく「犯罪」であり、企業の代表者や安全衛生担当者が処罰される可能性があります。悪質な場合、書類送検され、報道されるリスクもあります。
具体的には、
労働者死傷病報告義務違反(労働安全衛生法第100条、第120条第5号)
労働安全衛生法第100条第1項は、労働者が労働災害により死亡または休業した場合、事業者は遅滞なく「労働者死傷病報告」を所轄の労働基準監督署長に提出しなければならないと定めています。
労災隠しは、この報告を故意に行わない、または虚偽の内容で報告する行為であり、同法第120条第5号に基づき「50万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります。
これが労災隠しに対する最も直接的かつ一般的な罪名です。
両罰規定(労働安全衛生法第122条)
上記の違反行為があった場合、違反行為を行った実行者(例えば、現場の責任者や報告担当者)だけでなく、事業者(法人または事業主個人)も同様に罰金刑が科される可能性があります。これを両罰規定といいます。
虚偽公文書作成等の罪(刑法)
もし、労災隠しのために公務員に対して虚偽の申立てを行い、登記や戸籍などの公文書に不実の記載をさせた場合など、極めて特殊なケースでは刑法上の犯罪に問われる可能性もゼロではありませんが、一般的な労災隠しで直接適用されることは稀です。労働者死傷病報告書自体が刑法上の「公文書」に該当するかどうかは議論の余地があります。
したがって、労災隠しは主に労働安全衛生法違反(労働者死傷病報告義務違反)という犯罪に該当し、実行者だけでなく事業者も刑事罰(罰金刑)を受ける可能性がある重大な法令違反行為であるとご理解ください。
② 民事上の損害賠償リスク

労災事故について、企業は労働者に対して安全配慮義務(労働契約法第5条)を負っています。労災保険給付だけではカバーされない損害(慰謝料など)について、労働者から民事上の損害賠償請求を受ける可能性があります。
労災隠しという悪質な事実は、訴訟において企業側の過失や責任を重く認定させる要因となり、賠償金額が増額されるリスクを高めます。また、隠蔽行為自体が不法行為と評価される可能性もあります。
また、民事裁判においても、労災隠しをしたことは、会社側に不利に働くことはあっても有利に働くことはありません。裁判官の心証に対する悪化も避けられず、避けるべきです。
③ 社会的信用の失墜(レピュテーションリスク)
労災隠しが発覚すれば、報道などを通じて社会的に広く知られる可能性があります。
「従業員の安全を軽視する企業」
「法律を守らない企業」
というネガティブなイメージが定着し、顧客離れ、取引停止、株価下落、金融機関からの融資への悪影響など、事業活動全体に深刻なダメージを与えます。
特に近年は、企業のコンプライアンス意識やESG経営(環境・社会・ガバナンス)への関心が高まっており、労災隠しは致命的なダメージとなり得ます。
④ 人材確保・定着への悪影響
労災隠しを行うような企業で働きたいと考える人は通常おりません。
事件が明るみに出れば、採用活動が困難になるだけでなく、既存の従業員の士気低下や離職を招きます。優秀な人材ほど、企業のコンプライアンス意識や労働環境を重視するため、人材流出のリスクが高まります。
⑤ 労働基準監督署等による調査・指導の強化

労災隠しが発覚した場合、労働基準監督署は当該企業に対して厳しい目を向けることになります。過去の事案の徹底的な調査、より頻繁で詳細な立ち入り検査(臨検)、是正勧告、改善指導などが実施され、企業の管理負担が増大します。
他の法令違反(残業代未払いなど)も併せて調査され、問題が拡大する可能性もあります。
⑥ 労災保険料のメリット制への悪影響
労災保険料は、過去の労災発生状況に応じて保険料率が増減する「メリット制」が適用される場合があります。労災隠しによって一時的に保険料の増加を免れたとしても、発覚すれば遡って保険料が徴収される可能性があります。また、悪質な隠蔽があった場合、将来的なメリット制の適用において不利な扱いを受ける可能性も否定できません。
⑦ 根本的な安全対策の遅れ
労災隠しは、事故の原因究明と再発防止策の実施を妨げます。事故の根本原因が放置されるため、同様または更に重大な事故が再発するリスクを高めます。これは、従業員の安全を脅かすだけでなく、結果的に更なる経営リスクを招くことになります。
結論として、弁護士の立場からは、労災隠しは「百害あって一利なし」であり、絶対に避けるべき行為です。
短期的なコストや手間を惜しんで労災隠しを行うことは、発覚した際の法的責任、経済的損失、社会的信用の失墜といった、比較にならないほど大きなリスクを企業にもたらします。
事故が発生した際は、隠蔽することなく、法令に基づき誠実かつ迅速に対応し、原因究明と再発防止に努めることが、企業の持続的な発展にとって不可欠です。
労災事故における弁護士の役割
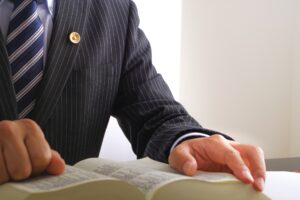
弁護士の役割
会社側の弁護士は、以下の点で重要な役割を果たします。
・従業員の請求根拠の法的検討
弁護士は従業員からの請求を法的観点から精査し、不当な請求を拒否したり、適切な減額を行ったりすることができます。
・労働トラブル対応と労働基準監督署対応
弁護士は会社側に適切なアドバイスやサポートを提供し、法的リスクを最小限に抑えることができます。
・適切な賠償額の算定
会社に対する安全配慮義務違反の主張に備え、違反があるといえるのか、違反があるとしてもどの程度の損害があり、損害に対して被災者の落ち度(過失)はどの程度か、など、弁護士は過去の裁判例を参考に、適正な賠償額を算定します。
これにより、会社は公平で合理的な補償を提供することができます。
・交渉・訴訟の代理人サポート
労災に強い弁護士が会社との交渉を行うことで、適切な解決策を見出すことができます。また、代理人として矢面に立つことで、会社側の無用で膨大な労力を削減することに繋がります。
会社側は、労災事故発生時に迅速かつ適切な対応を取ることが重要です。
同時に、法的リスクを最小限に抑えるため、弁護士のサポートを受けることで、従業員の権利を尊重しつつ、会社の利益も守ることができます。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの法人に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、労務手続に精通した弁護士が数多く在籍し、また、全弁護士の専門分野による顧問弁護士体制、使用者側の労働問題専門チームも設置しています。
このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士は、顧問先のお悩みや使用者の労務に関する法律相談を日々研究しておりますので、自信を持って対応できます。
お悩みの経営者・代表者の方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。
また、企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。