
近年社会問題化しているカスハラについて、令和7年6月4日、改正労働施策総合推進法が成立し、事業主がカスハラ対策を行うべきことが義務化されました。「企業のカスハラ対策」シリーズ第6弾である本稿では、この改正法の概要についてご紹介します。
カスハラ対策がいよいよ法制化

近年社会問題化していたカスタマーハラスメント(カスハラ)に対し、法整備を求める声の高まりを受け、令和7年6月4日、改正労働施策総合推進法が成立しました。
カスハラ対策を行うことにつき、これまでは、厚労省の告示(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」)による努力義務だったものが、これからは、いよいよ、事業主の法的義務となるのです。
改正法の施行は公布から1年半以内ですから、令和8年中には施行開始となります。
改正法では、カスハラとは、
①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
③労働者の就業環境を害すること
という3つの要件を全て満たすものを指すこととされました。
これまで、厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、カスハラを、
顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の従業環境が害されるもの
と定義してきましたので、今回の改正法はこの定義をほぼなぞったものと言えます。
つまり、どのような行為や言動がカスハラに該当するかは、改正法が施行される前と後とで、変わりはないものと言ってよいでしょう。
改正の概要

次に、具体的にどのような改正がなされたのか、カスハラ対策に関する部分に絞って確認していきます。
カスハラ対策を行うべきことが「事業主(企業、会社)」の法的義務とされたのみならず、「国」や「労働者」、「顧客等」にも一定の責務が課されているのが特徴です。
国の責務
国に対しては、次のように、「職場における労働者の就業環境を害する言動に関する規範意識を醸成するための国による啓発活動」を行うべきこととされました。
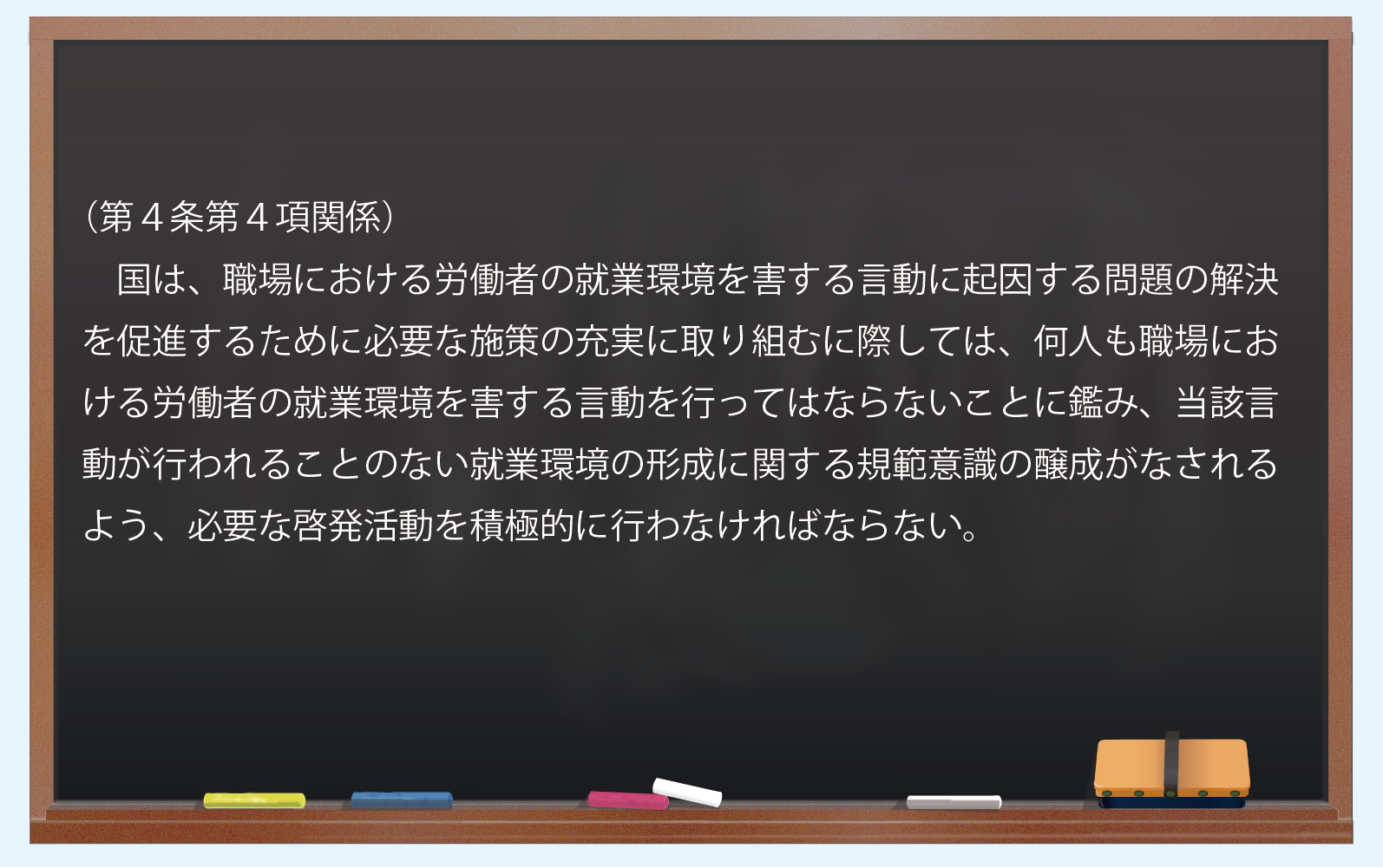
事業主の責務
事業主(企業、会社)に対しては、次のように、「職場における顧客等の言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等」が課されます。
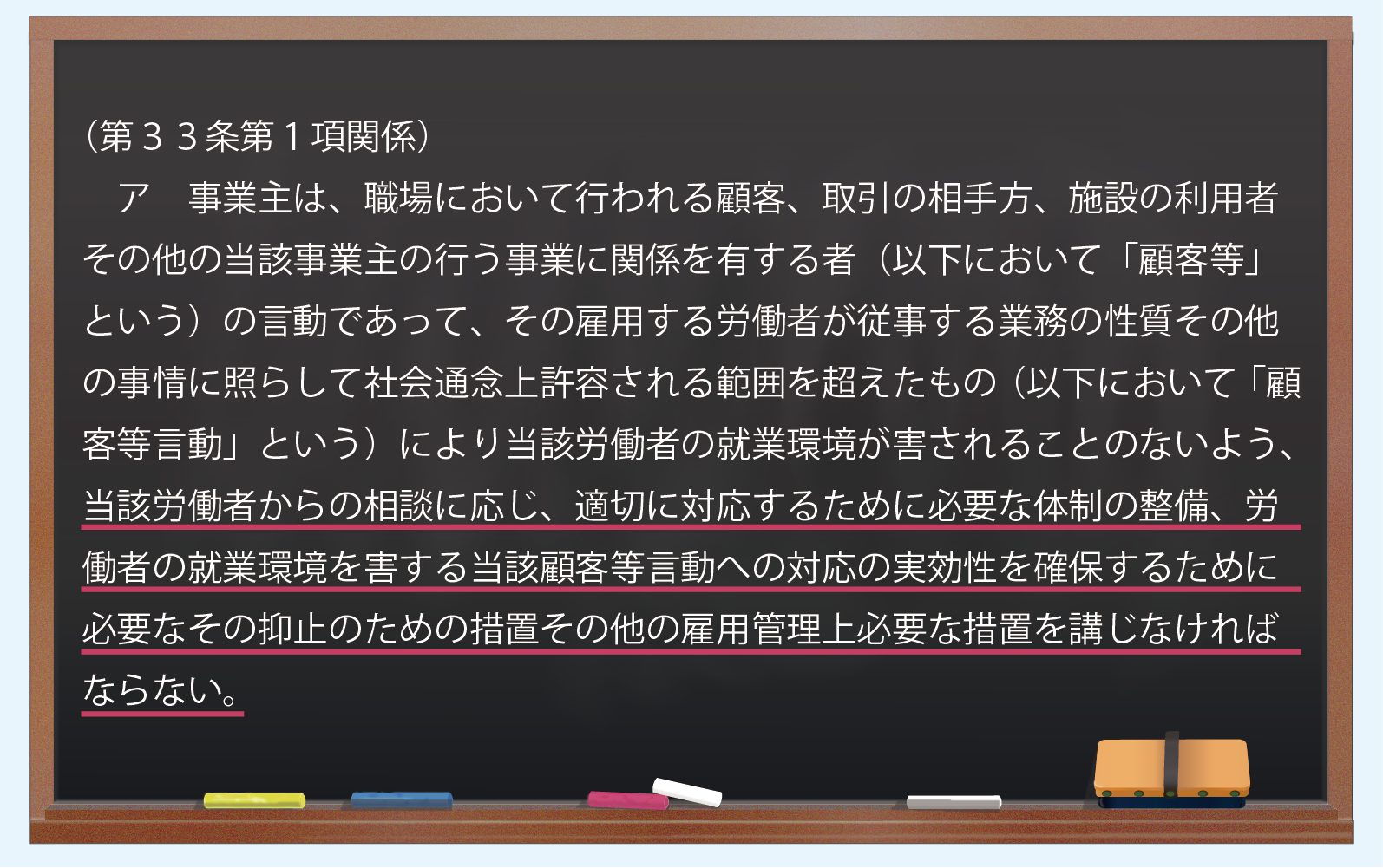
上記の中に、改正法が定めるカスハラの定義(①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、③労働者の就業環境を害することの3要件)が織り込まれているのが分かります。
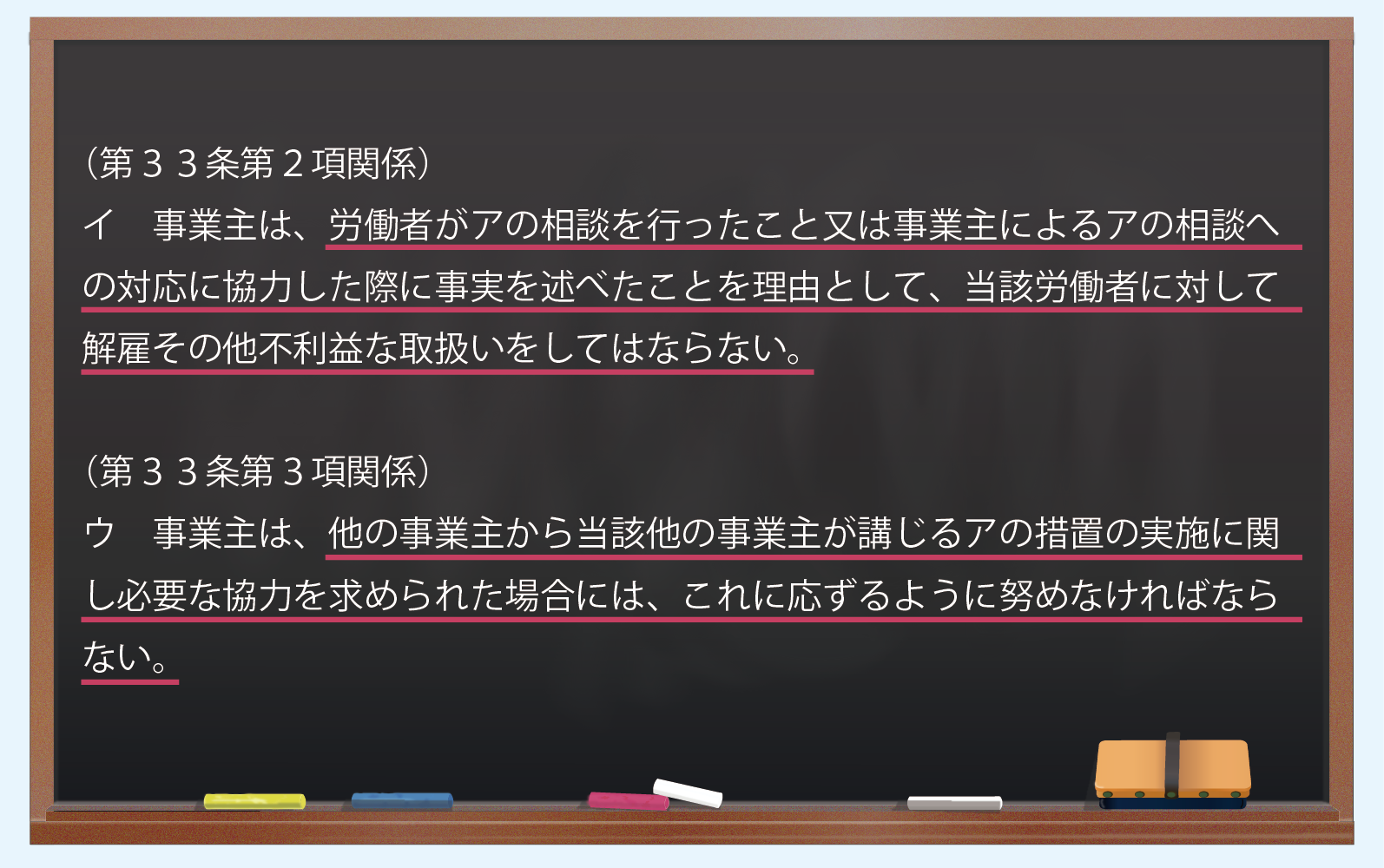
国・事業主・労働者・顧客等の責務

国や事業主のみならず、労働者や顧客等に対しても、「職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務」として次のような責務が課せられています。
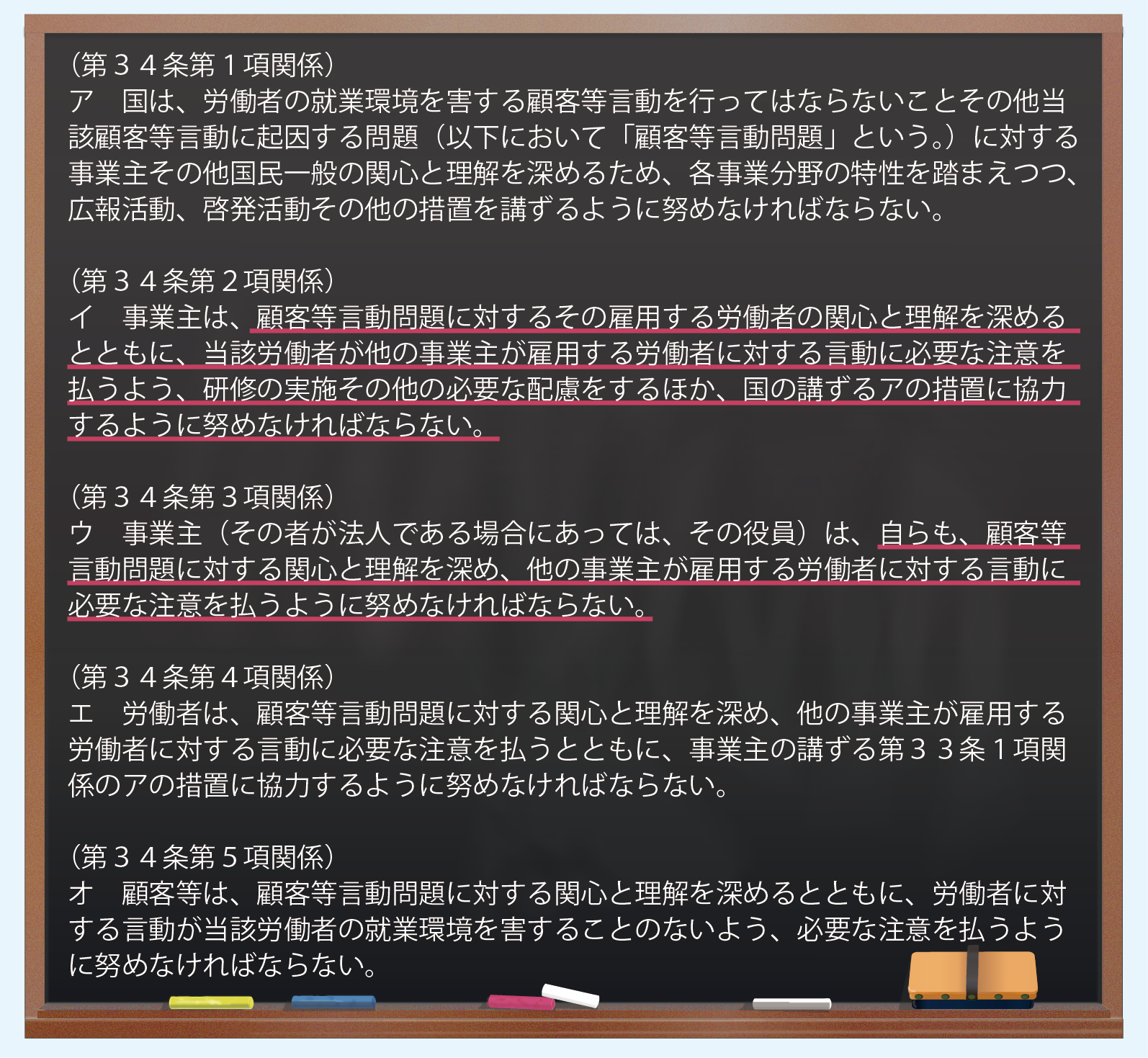
義務違反に対する行政処分

上記のとおり、改正労働施策総合推進法においては、法律上の義務として、事業主に対し、「職場における顧客等の言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等」(雇用管理上の措置義務)が課されることになります。
この義務に違反した事業主は、報告徴求命令、助言、指導、勧告または公表の対象となります。
近年、カスハラによって、対応する従業員が精神的に疲弊し、ひどい場合には休職や退職にまで追い込まれてしまうケースもあります。
人手不足の中、このような形で従業員を失うことは、言うまでもなく、企業にとっては大きな損失です。
また、カスハラによる被害が発生した時に適切な対応で従業員を守ってくれない企業、平素からカスハラに対する取り組みがいい加減な企業は、今後、新たな働き手となろうとする人からも、選ばれなくなってくるでしょう。
今回、ようやく、カスハラに関して雇用管理上の措置を取るべきことが法律上義務付けられました。
これまでこの分野での対策を怠ってきた企業は考え方を入れ替えて、法が要求する水準の取り組みを早期に始めるべきです。
また、これまでに一定程度の対策を行ってきた企業も、これを機に自社の取り組みを見直し、より一層の対策の充実を図ることが肝要です。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。
また、企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。










