
労働基準法施行規則第5条の改正により、令和6年4月1日から、労働契約の締結の際に全労働者に対して「就業場所・業務の変更の範囲」を明示することが義務化されました。この記事では、「変更の範囲」明示の内容や具体例、注意点について解説していきます。
労働条件明示義務とは
もともと、労働基準法は、労働契約(雇用契約)を締結する際に、労働条件を明示する義務を定めています。
労働基準法第15条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
※引用元:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
労働条件明示義務は、主として労働者が労働条件についてきちんと情報を得ることができるようにするための仕組みで、もし万が一、入社後の実際の労働条件が事前に示されていた労働条件と違った場合には、労働者に即時解除権が認められています(同法第15条2項)。
企業の視点から見れば、労働条件を明示することによって、条件の異同・違背を巡る将来の紛争を防ぐという効果がありますね。
さて、ここから今回のテーマに入っていきますが、そもそも「就業の場所」「従事すべき業務(の内容)」については、従前より、明示すべき条件として挙げられていました(労働基準法施行規則第5条1号の3)。
しかしながら、令和6年施行の改正では、そこからさらに一歩踏み込んで、「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」についても明示するべき条件に追加されたのです。
ちなみに、同改正では、有期労働契約の「更新上限の有無と内容」の明示と、「無期転換申込機会」及び「無期転換後の労働条件」の明示も新たに義務化されました。
有期労働契約を締結・更新する際は、こういった新しい明示義務にも注意して頂ければと思います。
「変更の範囲」の明示とは
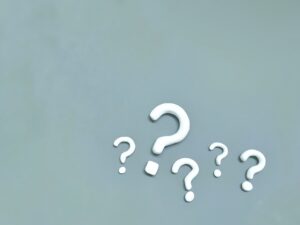
話を戻しますが、今回の改正によって、全ての労働者との間で、労働契約を締結する際と、有期労働契約を更新する際に、その契約期間中の就業場所・業務内容の「変更の範囲」の明示が必要になりました。
もとから明示すべきとされている「就業の場所」「従事すべき業務(の内容)」は、「入社した直後」の就業場所や従事する業務の内容を指すと言われています。
その上で、これまでは、労働契約の内容として職務内容や就業場所に限定を付ける合意がなされておらず、就業規則等によって包括的な配転命令権が規定されていれば、企業に対して異動・配置転換についての広い裁量を認めるというような解釈がされていました。
しかし今回の改正では、「将来的に」、異動・配置転換などによって就業場所や従事する業務の内容が変わり得る場合には、その変わり得る範囲についても、予め明示しておくべきとされました。
昨今では、介護や育児、共働き等の事情から、転勤を回避したいという労働者が増え、配置転換等に関連する紛争も増えたといわれています。
そのため、労働契約を締結するとき(入社するとき)に労働者にそのあたりの条件も明示して、労働契約を締結するかどうか最終ジャッジをさせて、予め覚悟してもらおうということで、今回の改正がなされたというわけですね。
「変更の範囲」の明示の具体例

上記のとおり、「変更の範囲」の明示は、将来的に変わり得る範囲を労働条件通知書等で明示しなくてはならないということですから、実際の企業の事情によって、記載の内容は様々だと思われます。
例えばシンプルな例で言えば、下記のような書き方があり得ます。
例:(就業場所)
入社後はさいたま支社勤務とする。ただし将来的に東京本社及び全国の支社、営業所での勤務を命じることがある。
例:(従事すべき業務の内容)
入社後…経理業務
変更の範囲…会社の定める全ての業務
ポイントは、「入社直後」の就業場所・業務内容と、「将来的な(=変更の範囲の)」就業場所・業務内容とを分けて記載することです。
労働条件通知書のひな型に、「雇い入れ直後」「変更の範囲」と予め項目を分けておくと漏れが無くなり安心かと思います。
他にも記載の具体例が知りたいという場合には、厚生労働省が公開しているパンフレット が分かりやすいと思いますので、よろしければご参照ください。
「変更の範囲」が「なし」または明示されなかったら?

上記のとおり、「変更の範囲」を明示することが義務化されたわけですが、実際には従前の労働条件通知書を利用してしまって変更の範囲を明示し損ねてしまったとか、「変更の範囲」について「なし」と書いてしまったということがあるかと思います。
こういった場合に、配置転換して就業場所や業務内容を変更しても良いのでしょうか?
これについて示した判例はまだありませんが、従前の裁判所の考え方を踏襲するとすれば、「変更の範囲」の記載は、締結された労働契約の内容を明らかにする上で、大きな手掛かりにされるのではないかと考えられます。
すなわち、例えば、労働条件通知書に「入社直後の就業場所:さいたま支社」「変更の範囲:なし」と記載されていたとしましょう。
この場合、わざわざ将来のあり得る就業場所について「なし」と書いたのですから、「会社としてはさいたま支社以外で働かせることは考えていないのだな。それを労働者側も受け入れて労働契約を締結したのだな。」と契約当事者の意思を解釈することが合理的(自然)ではないでしょうか。
このように裁判所も考えて、「この労働契約では、就業場所はさいたま支社に限定されている」と判断される可能性が高くなる、ということです。
あくまで解釈の話なので、もし事実がこれとは異なるという場合には、その事実を証拠でもって主張することになります。
一方、例えば、「変更の範囲」について、労働条件通知書等では項目が無い、触れられていないという場合はどうでしょうか。
義務違反であるという点は置いておいて、この場合には、「変更の範囲の明示」という、労働契約の解釈をするための手がかりが無いということになります。
したがって、その他の様々な事情から、就業場所や職務の限定合意があったかどうかを判断するということにならざるを得ないと思われます。すなわち、従前どおりということですね。
この辺りは、今後、改正法のもとでの運用が積み重なっていくことで、裁判所の判断も示されるかもしれませんので、都度最新の情報を確認して頂ければと思います。
「変更の範囲」明示の注意点、罰則など

そのほか、「変更の範囲」を明示するに当たっては、下記のような細かい点にも注意が必要です。
・在籍型出向があり得る場合は、出向先も「変更の範囲」として明示が必要
・臨時的な他部署への応援、出張、研修等、一時的に就業場所や従事すべき業務が変更される場合には明示は不要
・テレワークが想定される場合には、「雇い入れ直後」の就業場所や就業場所の「変更の範囲」として、「労働者の自宅」「サテライトオフィス」「会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)」等と明示する
また、「変更の範囲」の明示を含む、労働条件の明示義務の違反があった場合、労働基準法120条1号により、会社には30万円以下の罰金が科される可能性があります。
送検され罰金を科されるというところまでいってしまうと、刑事事件として新聞やニュースで企業名が公表されてしまうことも考えられますので、信用低下、企業イメージの低下など、罰金の金額以上のダメージを負うことになってしまいます。
それより以前には、労働基準法違反の事実を調査するために、労働基準監督署による立ち入り検査(「臨検」といいます。同法第101条1項)が行われたり、違反の事実が判明すれば是正勧告が出されたりすることが想定されます。
そもそも違反しないということが一番重要ですが、もし万が一違反してしまったという場合には、労働基準監督署の調査に協力し、早期に状況を改善して、影響を最小限にとどめることが肝要となります。
この記事をご覧になったことをひとつのきっかけに、今一度、貴社の労働条件通知書等をご確認頂けましたら幸いです。
まとめ

いかがだったでしょうか。
「変更の範囲」の明示義務は、令和6年4月1日から施行されていますので、記事執筆時点(令和7年8月)で、すでに1年以上経過していることになります。
毎年新入社員を採用しているような企業では、すでに労働条件通知書等のひな型を修正してあるかもしれませんが、特に採用は数年に1度というような企業では、まだ修正に未着手かもしれません。
これから秋になると、新卒の内定通知の時期が来ます。
その前に、今一度、貴社の労働条件通知書等の記載をご確認頂ければと思います。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。
また、企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。










