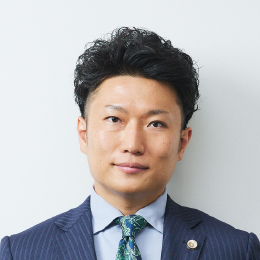はじめに
労働災害(労災)が発生した際、多くの場合は「労災指定医療機関」で治療が行われ、「様式5号」の書類が使用されます。しかし、救急搬送先が指定外の病院であったり、近隣に指定医療機関がなかったりする場合には、「様式7号」を用いた手続きが必要となります。
この様式7号は、従業員本人が手続きの主体となる部分が多いものの、会社(事業主)の証明が不可欠であり、その対応を誤ると手続きの遅延や労働基準監督署からの問い合わせにつながる可能性があります。
本記事では、使用者側の労災案件を専門的に扱う弁護士が、従業員から様式7号への証明を求められた際の、企業の正しい対応と実務上の注意点について解説します。
労災保険様式7号の基本~様式5号との違い~

まず、混同されがちな「様式5号」と「様式7号」の違いを明確に理解することが重要です。
様式5号(療養(補償)等給付たる療養の給付請求書)
労災病院や労災保険指定医療機関で治療を受ける際に使用します。医療機関の窓口に提出すれば、従業員は治療費を支払うことなく治療を受けられます(これを「現物給付」と呼びます)。書類は医療機関を経由して労働局に提出されます。
様式7号(療養(補償)等給付たる療養の費用請求書)
労災指定医療機関以外の病院や薬局で治療を受けた際に使用します。この場合、従業員は治療費の全額を一度医療機関に支払い、後日、労働基準監督署に様式7号を提出して、立て替えた費用を自身の口座に振り込んでもらう形で支給を受けます(これを「現金給付」と呼びます)。
使用者としては、従業員が指定外の医療機関を受診した場合、「従業員が一時的に治療費を全額自己負担する必要がある」という点をまず念頭に置き、手続きを円滑に進めるためのサポートが求められます。
事業主の責任~「事業主証明」の役割と注意点~

様式7号の申請手続きにおいて、会社が最も重要な役割を果たすのが「事業主証明」の欄です。ここには、事業所の名称、所在地、事業主の氏名などを記入し、申請書に記載された内容が事実であることを証明します。
この証明を行うにあたり、特に以下の点に注意が必要です。
災害発生状況の事実確認
「災害の原因及び発生状況」の欄には、「どのような場所で、どのような作業中に、どのような原因で災害が発生したか」が具体的に記載されます。事業主は、この記載内容が客観的な事実と相違ないか、十分に確認する義務があります。この内容が不十分であったり、事実と異なっていたりすると、労働基準監督署による調査が入り、手続きが長期化する原因となります。
派遣・下請労働者の場合の証明者
被災した労働者が派遣労働者である場合、証明は派遣元の事業主が行います。また、下請事業の労働者である場合は、元請の事業主が証明を行う必要があります。誰が証明義務を負うのかを正確に把握しておくことが重要です。
申請遅延・返戻を防ぐために使用者が確認すべき7つのリスク

様式7号は従業員が記入する項目が多いものの、事業主が事前にチェック・指導することで、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。差し戻し(返戻)や支給遅延を招かないために、会社担当者が確認すべき主なリスクは以下の通りです。
書式の取り違え
様式7号には、医療機関用の「(1)」、薬局用の「(2)」、柔道整復師用の「(3)」など、対象機関ごとに5つの種類があります。例えば、病院の治療費を請求するのに薬局用の書式を使っていないか、提出前に確認しましょう。誤った書式では受理されません。
業務災害と通勤災害の混同
労災には「業務災害」と「通勤災害」があり、使用する様式が異なります。通勤中の災害の場合は「様式第16号の5」を使用します。この区分を誤ると、根本的な申請のやり直しとなり、大幅な時間のロスにつながります。
労働保険番号の誤記
会社ごとに割り振られている14桁の労働保険番号は、正確に記載されている必要があります。不明な場合は、管轄の労働基準監督署に問い合わせて確認してください。
対象外費用の混入
労災保険の対象は、あくまで「療養のために通常必要なもの」です。希望による個室の差額ベッド代や、労災保険適用外の先進医療などが含まれていないか注意が必要です。これらが含まれていると、減額査定や審査の遅れにつながります。
添付書類の不備
従業員が立て替えた費用の支払いを証明する領収書の添付は必須です。また、はり・きゅう、マッサージ等の施術費用を請求する際には、初回の請求時や一定期間経過後に医師の診断書や意見書が必要となる場合があります。これらの添付漏れがないか確認を促しましょう。
振込先口座情報の誤り
審査が無事に終わっても、従業員本人の氏名や振込先口座情報に誤りがあると、費用の振り込みができません。特に、ゆうちょ銀行口座を指定する場合は、記号・番号の桁数に関する特有のルールがあるため注意が必要です。
「災害の原因及び発生状況」の記載不備
この欄の記載が「倉庫で転倒した」などの簡潔すぎるものだと、労働基準監督署が業務遂行性を判断できず、追加の報告を求められたり、調査が入ったりする可能性があります。5W1Hを意識した、客観的で具体的な状況説明がなされているかを確認することが肝要です。
提出先とその他の労災給付について

提出先
様式7号の提出先は、医療機関ではなく、所轄の労働基準監督署長です。この点も様式5号と異なるため、従業員に正しく案内しましょう。
その他の主な労災給付
労災保険には、治療費を補償する「療養(補償)等給付」以外にも、以下のような給付制度があります。企業としても、これらの制度を理解しておくことが重要です。
休業(補償)給付
労災による休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が支給されます。
障害(補償)給付
症状が固定し、後遺障害が残った場合に、障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。
傷病(補償)年金
療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、傷病等級に該当する場合に支給されます。
遺族(補償)給付
労働者が死亡した場合に、その遺族に年金または一時金が支給されます。
労災様式7号の手続きでお困りの企業様へ

様式7号の手続きは、従業員とのコミュニケーションに加え、労働基準監督署への正確な報告が求められる、使用者にとっても重要な業務です。特に、「事業主証明」は会社の責任を伴う行為であり、災害状況の記載内容によっては、後の安全配慮義務違反などの問題に発展する可能性も否定できません。
もし、申請内容の事実に疑義がある場合や、手続きに少しでも不安を感じる場合は、安易に証明するのではなく、速やかに使用者側の労働問題に精通した弁護士にご相談ください。専門家として、事実関係を法的な観点から整理し、適切な対応をアドバイスすることで、将来的なリスクを最小限に抑えるお手伝いをいたします。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの法人に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、労務手続に精通した弁護士が数多く在籍し、また、全弁護士の専門分野による顧問弁護士体制、使用者側の労働問題専門チームも設置しています。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士は、顧問先のお悩みや使用者の労務に関する法律相談を日々研究しておりますので、自信を持って対応できます。
お悩みの経営者・代表者の方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。
また、企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。