
従業員の能力不足は、多くの企業が直面する課題です。
従業員のパフォーマンスが企業の業績に直結するため、その対応は避けて通れません。
しかし、その対応策として「減給」を検討する際、法的な問題が考えられます。
本ページは、弁護士の立場から、従業員の能力不足を理由とする減給が法的に認められるか、そして適法に減給を行うための要件や注意点について、解説します。
減給の法的根拠と原則について

労働契約法第8条は、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約を締結し、変更することができる」と定めています。
つまり、労働条件の変更には、原則として労働者の同意が必要です。
この原則は、労働者保護の観点から非常に重要であり、使用者の一方的な労働条件の不利益変更は厳しく制限されています。
従業員の能力不足を理由とする減給は可能か?

結論から申し上げますと、従業員の能力が不足する場合でも、それだけの理由で一方的に減給することは原則としてできません。
その理由は、給料の額は雇用契約で定められているからです。
一度締結した契約の内容を労働者との合意無くして変更することは許されないため、雇用契約の内容である給料の額を強制的に減らすことは原則としてできないのです。
しかし、従業員の能力が著しく不足する場合にも一切減給できないのでは、会社側の不利益が大きくなります。
そこで、「一定の事由」がある場合には、例外的に能力不足を理由として減給することも可能です。
能力不足を理由に減給する方法について

労働契約法第9条は、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」と定めています。
ただし、同法第10条には、以下のような例外が定められております。
「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、変更後の就業規則に定めるところによる」
つまり、能力不足を理由とする減給を適法に行うためには、この「変更の合理性」が極めて重要なポイントとなります。
適法な減給方法について

では、具体的にどのような方法であれば、能力不足を理由とする減給が適法と判断されるかについて、その要件は、以下の通り多岐にわたります。
1 就業規則・賃金規程の明確な定め
前提条件として、就業規則や賃金規程に、能力評価に基づく減給の規定が明確に定められていることです。
特に、以下の点を明確にしておく必要があります。
・評価制度の存在: 減給の根拠となる人事評価制度が明確に存在すること
・評価基準の客観性: どのような能力・成果を評価するのか、その基準が客観的かつ具体的に定められていること。抽象的な「能力不足」といった表現では不十分です。
・減給の算定方法: 評価結果に応じて、どの程度の減給が行われるのか、その算定方法が具体的に定められていること。
これらが明確でなければ、減給は恣意的なものと判断され、無効となるリスクが高いです。
2 雇用契約の変更による減給
契約内容を一方的に変更することはできませんが、当事者双方が合意すれば変更可能です。
事前に能力が不足する従業員と話し合い、双方が納得する給料の額で合意し、雇用契約の内容を変更すれば、減給することができます。
もっとも、従業員には納得の上で合意してもらうことが重要ですので強引に合意を押し付けるなどの態様により雇用契約の変更を押しつけた場合は、形式的には合意があったとしても、真意に基づく合意ではないと判断され、減給が無効となるおそれもありますのでご注意ください。
3 人事評価による減給
会社の人事評価においてスキルや業績に応じて、待遇に差異を設けるシステムを採用している場合、能力不足の社員の人事評価を適正に行うことにより、減給できる可能性があります。
もっとも、特定の従業員の能力が所定の基準に満たないとしても、いきなり減給するとトラブルになりやすいです。
会社としては、対象従業員について、どのような能力がどの程度欠如しているのかを冷静に判断し、必要な注意・指導・研修を行うことをオススメします。
それでも、改善がみられない場合に減給を検討する必要があります。
また、人事評価による減給を行う場合の注意点については先ほどご説明した点のとおりです。
懲戒処分による減給
従業員の能力不足が著しい場合は、懲戒処分を行うことで減給できる可能性があります。
懲戒処分とは、企業の秩序や職場の規律に違反した従業員に対して、企業側が下す制裁のことです。
対象従業員の減給につながる可能性のある懲戒処分には、次の3種類があります。
・減給:その名のとおり、対象従業員へ支給する給料から一定額を減らす処分
・出勤停止:一定の日数につき出勤させない処分のことであり、対象従業員が出勤しなかった日数分だけ減給になる
・降格:下位の役職へ降ろす処分のことであり、役職に応じて待遇に差がある場合には、結果として減給になる
懲戒処分を行うためには、就業規則に懲戒処分の種類と、種類ごとに該当する事由が定められていなければなりません。
もっとも、能力不足という理由だけで減給を伴う懲戒処分を下すことは困難であります。
能力不足を理由に減給する際の注意点

従業員の能力不足を理由に減給する場合、以下の点に注意する必要があります。
1 合意的な理由がなければ違法になる
当該従業員の能力不足が、減給に相当するだけの「合理的な理由」にあたると言えない場合、その措置は違法となります。
「合理的な理由」があることを説明できるようにするためにも、当該従業員について、どのような能力がどの程度欠如しているのかを具体的に、かつ、なるべく客観的に把握することが重要です。
対象従業員に減給措置について納得してもらうためにも、その仕事ぶりを記録して証拠化しておくことは重要です。
2 適切な手続きを踏まなければ無効となる
適正な手続きを踏まずに懲戒処分を行う場合、その処分が社会通念上相当であることを確認する手続を怠ったことになるため、権利の濫用として懲戒処分が無効となる可能性があります(労働契約法第15条)。
まず、減給を行うか検討する場合、、就業規則や雇用契約の定めに従って手続きを進めなければなりません。
また、当該従業員に対して必要な注意・指導・研修を行うべきです。
その従業員の不足部分を見極め、その部分について重点的に教育するというように、実効的な指導が必要です。
そして、実際に減給などの懲戒処分を行う際には、対象となる問題行為の事実関係を確認して証拠を確保した上で、その従業員の行為が就業規則に定めた懲戒事由に該当することについて、弁明の機会を与えることも必要です。
3 懲戒処分としての減給を行う場合、上限がある
労働基準法第91条は、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」と定めています。
これは、懲戒処分としての減給を念頭に置いたものです。
したがって、懲戒処分としての減給を行う場合、上限があるため慎重な計算が必要となります。
なお、この上限規制に違反して過大な減給処分をすると、会社側に「30万円以下の罰金」という刑事罰が科せられるおそれもあるので、注意(労働基準法第120条第1号)。
まとめ
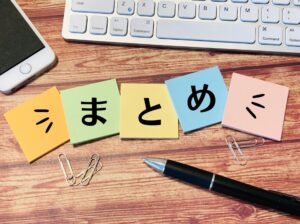
以上、従業員の能力不足を理由とする減給を適法に行うための注意点等について解説しました。
能力不足は、従業員個人の問題だけでなく、企業のマネジメント体制や評価制度の問題でもある可能性があります。
安易な減給に走るのではなく、まずは教育・指導を通じて従業員の能力向上を支援することが、長期的に見て会社の成長につながる最も重要な策と考えられます。
減給はあくまで最終的な手段であり、その実施には極めて慎重な対応が求められます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。
また、企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。










