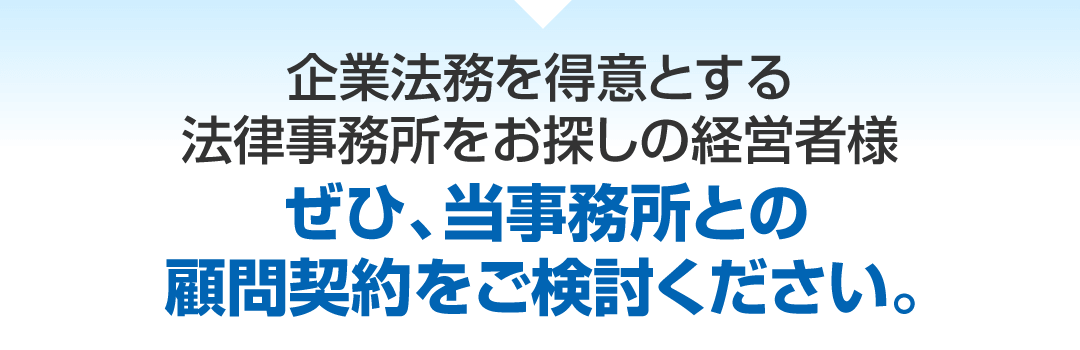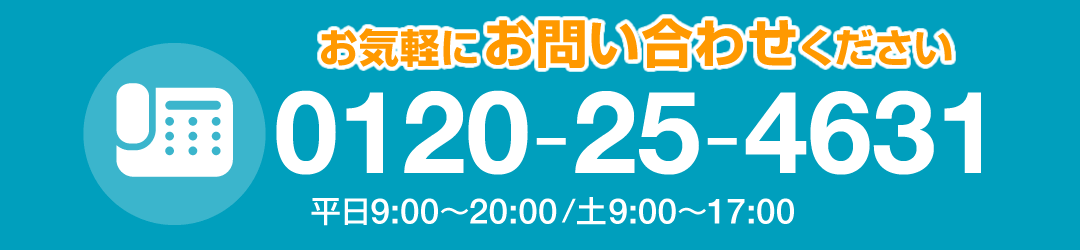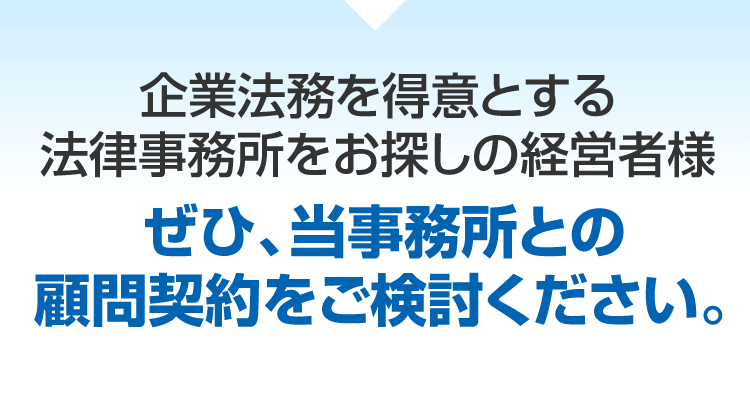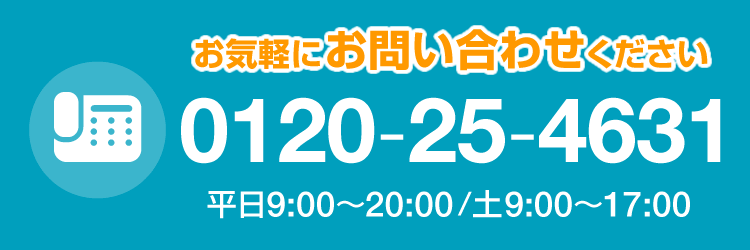労働者が使用者に対し未払の残業代などについて請求する場合、付加金の支払を併せて請求することがあります。使用者として注意するべきこと、できることはたくさんありますので、この記事では、付加金について詳しく解説します。
1 付加金について
(1) 付加金とは?
労働事件の裁判のニュースなどで「付加金」という言葉を聞いたことはないでしょうか。
付加金とは、残業代等の未払に対するペナルティのことです。
付加金は、労働基準法により定められた制度でして、次のように規定されています。
労働基準法 第114条(付加金の支払)
裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第7項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。
つまり、時間外割増賃金等の未払いがある場合、労働者の請求があれば、裁判所は、使用者に対し、未払の時間外割増賃金等と同じ金額(つまり合計すれば2倍の金額)の支払いを命じることができるのです。
これは、アメリカの付加賠償金制度を参考に設けられた制度でして、残業代等の支払を行わなかった使用者に対する制裁の意味を持つ制度です。
条文を見ると、「労働者の請求により」とあるように、労働者からの請求が無ければ付加金の支払は命じられませんし、「命ずることができる」とあるように、付加金の支払を命じるかどうかは、裁判図が具体的な事情を考慮して決めることになります。裁判所が当該事案の悪質性は低いというように判断した場合、付加金の支払は命じられないことになります。
裁判所が付加金の支払を命じる前に、使用者が未払金の支払を完了し、労働基準法違反の状態が消滅すれば、労働基準法114条の要件を満たさないことになるので、裁判所は付加金の支払を命じることはできなくなります。
(2) 付加金の対象となる金銭
付加金の対象となる金銭は、以下のものになります。
以下のお金の未払いがある場合、労働者は使用者に対し、付加金の支払を請求することができます。
ア 解雇予告手当(労働基準法20条)
労働基準法20条では、使用者は労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。
この30日分以上の平均賃金が解雇予告手当です。
「30日分以上」とありますので、実務上は、30日(1ヶ月)分の給与が支払われることがほとんどです。
使用者が解雇の予告も解雇予告手当の支払もなく労働者を解雇した場合、労働者は使用者に対し、解雇予告手当の支払を請求することができますが、その際に、付加金の支払を請求できることがあるのです。
イ 休業手当(労働基準法26条)
労働基準法26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、使用者は、休業期間中当該労働者にその平均賃金の100分の60(6割)以上の手当(休業手当)を支払わなければならないとしています。
つまり、労働者が休業しなければならなくなった原因が専ら使用者にある場合に問題となります
休業手当が問題になるケースとしては、使用者が所有し管理する設備等が故障し、それを使用して働く労働者が労働することができなくなった場合などが挙げられます。
ウ 残業代(労働基準法37条)
労働基準法37条は、使用者が労働者を時間外・休日に労働させた場合には25%以上増額した賃金を支払わなければならないとしています。また、使用者が労働者に深夜(午後10時から午前5時の間)に労働をさせた場合には、25%以上増額した賃金を支払わなければならないとしています。
休日・深夜労働が重なった場合、割増賃金は加重されることになります。
また、いわゆる管理監督者であっても深夜割増は発生しますので、注意が必要です。
実務上は、この残業代の請求が行われることが多く、付加金の請求も行われることが多いです。
エ 有給休暇中の給料(労働基準法39条9項)
労働者が有給休暇(年次有給休暇)を取得した場合、基本的には、通常の金額の賃金が支払われることになります。有給休暇については、事前の申出や使用者による時季変更権などが問題になり得ますので、これらについても注意が必要です。この未払があった場合も、未払い分の請求と共に、付加金の請求をすることができます。

(3) 付加金の請求期限
付加金には請求できる期限が定められています。
1(1)でご紹介した労働基準法114条によりますと、付加金の請求期限は、「違反のあった時から2年以内」とされています。
当初は、付加金を請求できる期間は2年間とされていましたが、2020年4月施行の改正民法の影響で延長され、3年間とされています(なお、労働基準法114条但書の条文上は5年とされていますが、同法143条2項にて、当面の間は3年間とされています。)。
割増賃金の請求期限には時効という制度があり、時効は完成猶予や更新により進行を止めたり遅らせたりすることができます。
しかし、付加金の「2年以内」という期間は、除斥期間というものであり、時効と異なり完成猶予や更新という制度がないので、進行を止めたり遅らせたりすることはできません。
もし労働者から付加金の支払を請求された場合、付加金請求の期限を過ぎていれば、このことを主張し、付加金請求に反論することができます。
そのため、使用者としては、労働者から付加金の支払を請求された場合、まずは付加金の請求期限が過ぎていないかどうかを確認しましょう。
2 付加金の支払が認められるには
付加金は、賃金等の未払いに対するペナルティですので、未払が悪質である場合に認められます。
付加金が認められる場合に関しては、労働基準法に明確な規定がないため、裁判所が裁判において判断し、判決で命じることができるという形態となっています。未払い賃金があれば必ず付加金の支払いが命じられるというわけではなく、どのような場合に命じられるのかも規定はありませんが、使用者の賃金未払いが悪質であると判断された場合に、制裁の意味合いで科されることが多いといえます。
付加金の支払いは、裁判所の命令があって初めて生じます。つまり、付加金の要件として、次の2点を満たさなければ、会社側は付加金を支払う義務を負いません。
1. 付加金の対象となる賃金に未払いがあること
2. 付加金の支払いを裁判所に命じられたこと
このとき、「裁判所」というのは訴訟のことを意味しており、労働審判を行う労働審判委員会は「裁判所」に含まれません。つまり、労働審判では、付加金の支払いが命じられることはありません。
また、訴訟においても、付加金の支払いを命じるかどうかは裁判所の裁量に任されており、必ず支払いを命じなければならないわけではありません。交渉態度が不誠実であったり違反の程度が悪質であったりといった、制裁の必要性が高い場合にはじめて、裁判所は付加金の支払を命令します。

3 付加金の支払について判断がなされたケース
(1)アートコーポレーションほか事件(東京高裁令和3年3月24日判決)
引越会社の従業員であった原告が、会社である被告に対し、残業代請求等を行った事案です。
一審判決は、付加金の支払を認めませんでした。
その理由として、①残業代が一部未払いだったが、大部分は支払い済みだったこと、②訴訟提起前の団体交渉時から、会社が未払いの残業代を支払う意思を示していたこと、といった事情が挙げられています。
これに対し、控訴審は、一審判決とは異なり、付加金請求を認容しました。
「一審判決によって未払時間外割増賃金等が一部存在することや未払に対する法律上の主張に理由がないとの判断が示されているにもかかわらず、その後も支払拒絶を継続しており、控訴理由に照らしても合理的とはいいがたく、付加金の支払を命じるのが相当である」としています。
一般的に、付加金の支払いについては、労働基準法違反の程度や態様、労働者の不利益の性質、内容、違反に至る経緯やその後の会社の対応などの事情を考慮して決めるべきとされています(コーダ・ジャパン事件:東京高裁平成31年3月14日判決)。
本判決は、一審判決後の会社の対応を考慮した結果、付加金を命じたものといえます。
(2)未払残業代と付加金併せて約180万円の支払が命じられた事例(最一小判平成14年2月28日)
警備業の男性が、宿直での仮眠も労働時間にあたるとし、未払い残業代などの支払いを勤務会社に求めた事例。
当該労働者は、被告会社において、ビルの警備員の業務を行っていたが、勤務は24時間制で、その中で4時間30分の仮眠時間と30分の休憩時間が設けられていました。
しかし、労働者には、休憩・仮眠時間のあいだも、通報等が入ればすぐに対応できるように要請されており、実際、仮眠中であっても通報等があればすぐに対応できる体制がとられていました
裁判所は、そのような状況においては、休憩・仮眠時間も業務から解放されているとはいえないため、ほぼ原告の請求通り、未払い残業代と付加金の計約180万円を支払うよう命じました。
この判例は、付加金の支払について判断した点以外にも、仮眠時間が労働時間にあたると判断した点で意義のある判例です。
(3) 付加金の支払が認められなかった事例(最二小判昭和35年3月11日)
洋服の製作・修理を業とする会社に勤務していた原告が被告である会社に対し、未払の時間外割増賃金等を請求した事件
裁判所は、「労働基準法一一四条の附加金支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場合に、当然に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって、初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に労働基準法二〇条の違反があっても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は同条による附加金請求の申立をすることができないものと解すべきである。」と判断しました。
使用者に労働基準法37条等の違反があっても、既にその支払いを完了し、使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は労働基準法114条による付加金請求の申立てをすることができないと判断しました。
(4)付加金の支払が認められなかった事例(最二小判昭和51年7月9日)
商人に雇用された労働者が商人に対し、未払の割増賃金等の支払を求めた事件です。
裁判所は、「なお労働基準法一一四条の附加金の支払義務は、労働契約に基づき発生するものではなく、同法により使用者に課せられた義務の違背に対する制裁として裁判所により命じられることによって発生する義務であるから、その義務の履行を遅滞したことにより発生する損害金の利率は民事法定利率によるべきものであり、」とし、裁判所が使用者に対し付加金の支払を命ずることはできないと判断しました。
(5)付加金の支払が認められなかった事例(最一小判平成26年3月6日)
労働者である原告が、会社である被告に対し、未払の未払いの割増賃金等の支払を請求した事件
裁判所は、「付加金の支払義務は、割増賃金の不払等によって当然に発生するものではなく、労働者の請求により、裁判所がその支払を命じることによって初めて発生するものであるから、事実審の口頭弁論終結時までに、未払割増賃金の支払を完了し、割増賃金の支払義務が消滅したときは、裁判所は付加金の支払を命じることはできなくなる。」と判断しました。
(6)付加金の支払を認めなかった事例(最三小判令和元年12月17日)
裁判所は、「労働者が付加金を請求していない月分については、労働者が当該月分の割増賃金請求権を請求しておりこれを認容できるからといって、付加金の支払を命じることはできない。」と判断しました。
つまり、労働者の側が支払いを請求していない分については、裁判所は付加金の支払を命ずることはできないと判断したのです。

4 付加金が認められない場合
訴訟において裁判所が付加金支払を命じないと判断すれば、付加金の支払が命じられることはありません。
その他にも、そもそも付加金の支払という方法が存在しない手続をあり、その場合、当然のことながら付加金の支払が命じられることはありません。
以下では、そのようなケースについて具体的に見ていきましょう。
(1)交渉事件で解決した場合
未払割増賃金等の請求については、裁判所を使った手続きではなく、当事者同士のやり取りを内容とする交渉事件で解決することもあります。
この場合、裁判所が介入するものではないので、付加金の支払が命じられることはありません。
(2)労働審判で解決した場合
労働審判とは、裁判所において行われる手続でして、原則として3回程度の期日で終了します。訴訟とは異なり、話し合いがベースとなっているのである程度柔軟な解決が期待できます。争点がそれほど多くない場合や当事者の主張にそこまで隔たりがない場合などにはこの手続の利用を考えるべきです。
労働基準法114条によれば、付加金は、「裁判所」が命じることができるとされています。労働審判を主催する労働審判委員会は、「裁判所」ではありませんので、労働審判においては付加金の支払が命じられることはありません。
(3)訴訟が和解で終了した場合
訴訟は、必ずしも判決で終了するのみではなく、和解で終了することも珍しくありません。
和解においては、当事者がお互いが譲歩できる条件を話し合い、お互いが妥協できるところで妥協し、和解条項を成立させることになります。
和解は判決とは異なる手続ですので、和解において付加金の支払が内容とされることは基本的にはありません。
(4)付加金の請求期限を過ぎた場合
2でご説明した通り、付加金には請求期限があります。
これを過ぎてしまうと、付加金の請求をすることはできません。
付加金は、時効とは異なり、完成猶予や更新という制度がないので、進行を止めたり遅らせたりすることができないことが特徴です。
5 付加金の支払を避けるためには
(1)交渉で解決する
5でも述べました通り、交渉で事件を終了させた場合、付加金の支払が命じられることはありません。また、交渉は、訴訟などの裁判手続きと比べて、当事者の話し合いがベースですので、柔軟な解決が期待できます。場合によっては、訴訟や労働審判よりも、労働者に支払う金額が低くて済むこともあります。
そのため、当事者の主張がそれほどかけ離れておらず、話し合いの余地がある事案でしたら、交渉での解決を目指すことを積極的に検討するべきです。
(2)労働審判で解決する
5でもの述べました通り、労働審判で事件を終了させた場合、付加金の支払が命じられることはありません。労働審判は訴訟と同じく裁判所を介在させる手続ですが、当事者の話し合いがベースとなっているものであり、訴訟に比べて柔軟な解決が期待できます。また、労働審判は原則、3回程度の期日で終了する手続ですので、訴訟と比べて時間や労力を少なく抑えることができます。そのため、交渉では解決できない場合でも、訴訟ではなく労働審判での解決を図るということも有効な選択肢のひとつです。
ただ、労働審判は原則として3回程度で終了する手続ですし、話し合いがベースとなりますので、争点がたくさんあるケースや当事者の主張がかけ離れており話し合いの目途がつかないようなケースには馴染みません。そのようなケースでは、訴訟による解決を目指すことになります。
(3)訴訟を見据えた対応をする
付加金の支払を命ずるかどうかは、使用者の交渉態度や違反の程度の悪質性等を考慮して裁判所が決定します。
割増賃金等の支払が発生しないようにするに越したことはありませんが、割増賃金等の未払いが生じてしまった場合は、訴訟になることも見据えて、できるだけ労働者との間で真摯に交渉を行うべきです。
また、未払いの割増賃金等が発生しないようにするためにも、従業員の勤怠・労働時間の管理をしっかりと行うことも重要です。これらの管理をしっかりと行っていれば、訴訟において付加金の支払が命じられる可能性を低くすることができます。
訴訟になることを見据えて、従業員の勤怠・労働時間の記録(タイムカードの打刻記録、パソコンのログイン・ログオフの記録、業務報告書、業務報告メールなど)をできる限り長い期間保管しておくことも重要です。
真摯に交渉を行えば、交渉や労働審判で解決できる可能性も高くなり、使用者側の希望を反映した条件で解決することのできる可能性も高くなります。
また、訴訟の中で、未払の割増賃金等について、会社に不利な判断がなされることがわかってきた場合、未払賃金を支払ってしまうというのも方法の一つです。
これと関連するものとして、訴訟を和解で終わらせるという方法もあります。5でもご説明しました通り、和解であれば、ある程度当事者双方の意向を反映した解決が期待できますし、柔軟な解決も見込めますので、和解による解決も検討するべきでしょう。
グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。ご依頼を受けた場合、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。